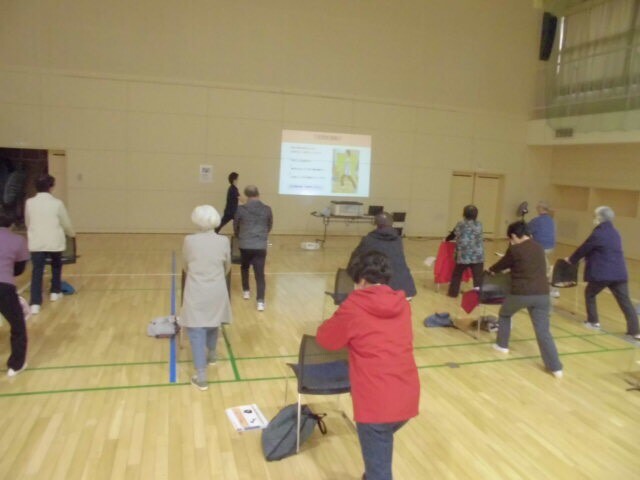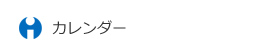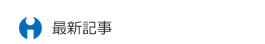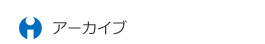(2021年4月26日 10:00)(外来リハビリブログ)
こんにちは!北星病院外来リハビリ班です。
朝練です。
今回のテーマは『胸郭出口症候群(きょうかくでぐちしょうこうぐん)』です。
胸郭出口症候群とは・・・
首と胸周辺を通る神経や血管があります。
その神経や血管が圧迫されたり引っ張られたりしてしまうことで
腕や手に痺れやむくみ、冷たさを感じるなどの症状が出ることがあります。
神経の通り道として
①前斜角筋と中斜角筋(首の筋肉)のあいだ
②鎖骨と第一肋骨とのあいだ
③小胸筋(胸の筋肉)のうしろ
があります。
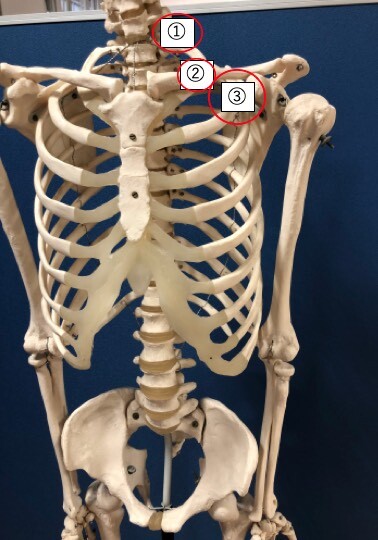
アプローチとして種類はいくつかありますが
リハビリで行うアプローチとしては
①・③の場所で起こるような神経の圧迫を改善するために
筋肉の柔軟性を出すためのマッサージや物理療法、姿勢や筋肉の過剰な
緊張を予防するための日常生活指導を行なっています。
当てはまるような症状の方は是非ご相談ください!
参考文献
Chi-ngai Christopher Lo Systematic review: The effectiveness of physicaltreatments on thoracic outlet syndrome in reducingclinical symptoms 2011