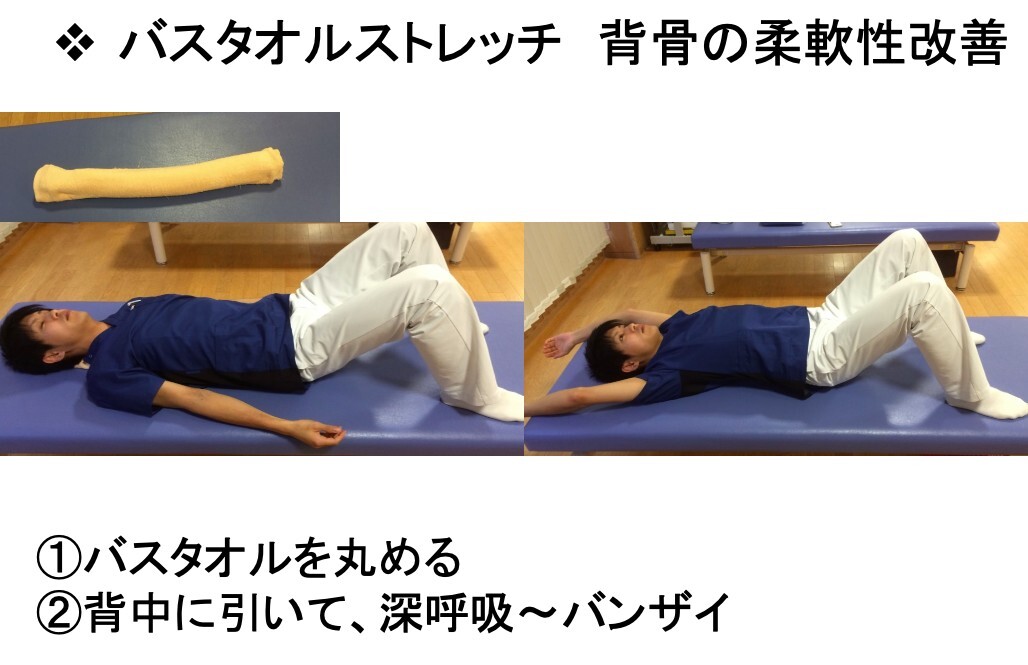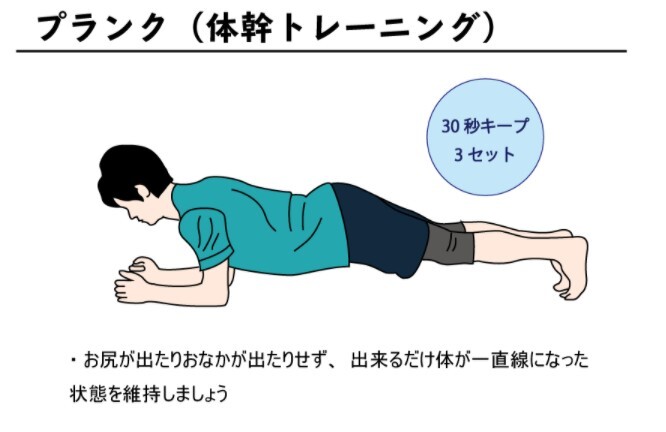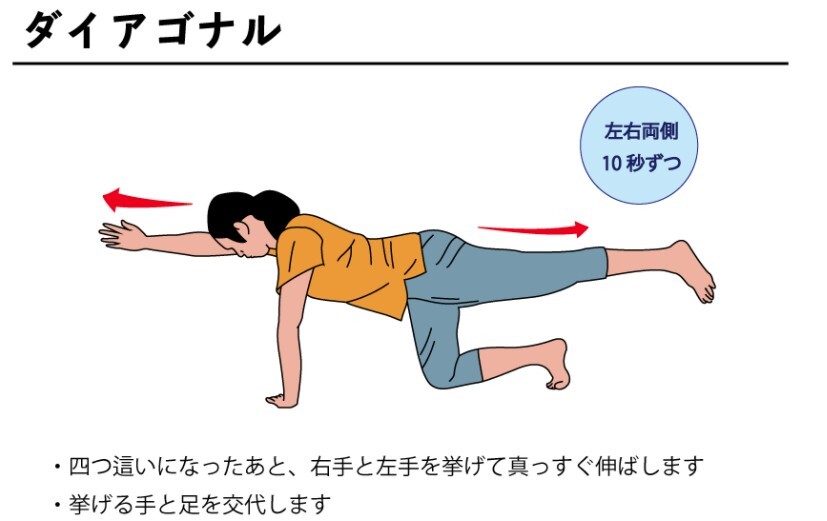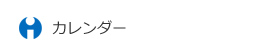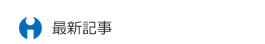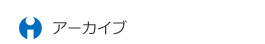(2021年6月11日 10:00)(通所リハビリブログ)
音楽療法士の青木梨央です。昨年4月から北星病院通所リハビリセンターで音楽療法を開始しました。“音楽療法”と聞くと、
言葉は聞いたことあるけどな~
音楽で癒すことかな~
など音楽療法のイメージは曖昧で、まだ馴染みのない分野かなと思います。
そこで、これから定期的に音楽療法の素晴らしさや、音楽が心や身体にどのような効果があるのかを掘り下げていき、皆様にお伝えしていきたいと思います!
初回の今回は、「音楽療法の歴史と今」についてです!
まず、音楽療法はいつからあるのか。
なんとその始まりは… 紀元前なんです!!
〈ギリシャ神話〉
登場するオルフェウスは竪琴弾きで、その音楽の力を病の治療に用いていたと記されている。
〈旧約聖書〉
ユダヤの王サウルの心の病を羊飼いの若者ダビデが竪琴を弾いて治した逸話がある。

ギリシャの哲学者アリストテレスは、『音楽には情緒を発散させるカタルシス効果がある』と述べ、プラトンは『音楽は魂の薬である』と述べています。
薬や医療が確立していなかった紀元前から、人は音楽の力を感じ、治療として音楽が用いられていたようです。
意外にも音楽療法の歴史は古かったのです!
20世紀になり、アメリカでは1956年から公認音楽療法士が誕生し、日本ではその約40年後の1997年に認定音楽療法士が誕生しました。
現在、日本の認定音楽療法士は2,461名(2021年3月末日現在)理学療法士は129,875名(2021年3月末日現在)であり、比較すると音楽療法士はとても少なく貴重で、これからさらに発展していく分野だと考えられます。
実際に通所リハビリセンターでは、感染症対策を行いながら音楽療法を毎日実施しています。
音楽を聴くだけではなく、音楽に合わせた身体活動や楽器活動、脳トレを組み合わせるなど、目的に応じて行っており、ご利用者様からも大変ご好評いただいております。
今後は、活動の場をリハビリセンター以外にも地域へと広げていきたいと考えています。ご興味のある方は、北星病院通所リハビリセンターまでご連絡下さい。
以上、『音楽療法の歴史と今』でした♪
次回は『音楽が気分や感情とどのような関係があるのか』をお伝えする予定です。お楽しみに♪
引用文献
William.B.Davis.,Kate.E.Gfeller.,Michael.H.Thaut.栗林文雄(訳)音楽療法入門Ⅰ