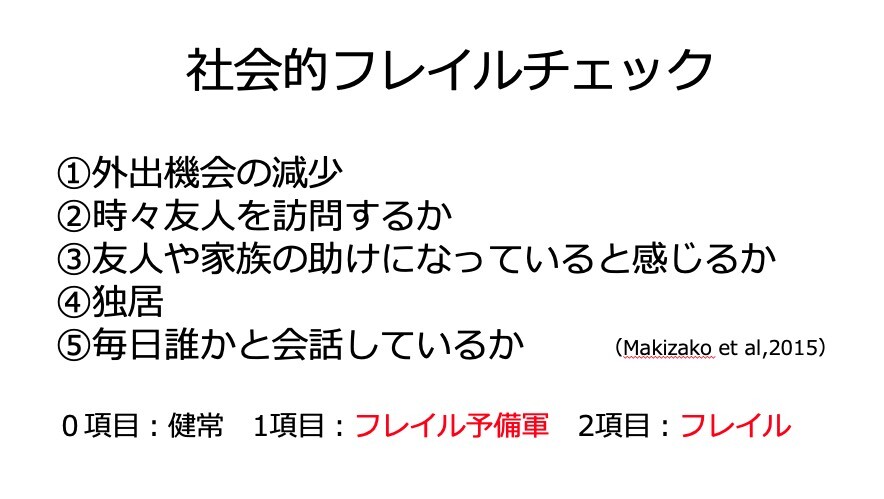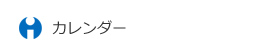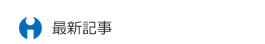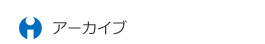(2020年12月11日 16:27)(外来リハビリブログ)
こんにちは!北星病院外来リハビリ班です。
本日は朝練です。
例題として
インナーマッスルが上手く使えず
腰痛が持続している症例でした。
インナーマッスルとは
横隔膜、腹横筋、多裂筋、骨盤底筋から
なる体幹の奥にある筋肉で
身体を安定させたりといった働きがあります。
その中でも本日は骨盤底筋に絞って行いました。

骨盤底筋はその名の通り骨盤の底にある筋肉で身体を支えることはもちろんのこと
尿漏れなどにも関連していると言われています。
骨盤底筋が硬くなっていたりすると
骨盤底筋自体や周りの筋肉が上手く動かなくなり腰痛に影響してきます。
今回は骨盤底筋、その周辺の筋肉の触診、骨盤底筋を動かす練習を行いました。
次回も頑張ります!